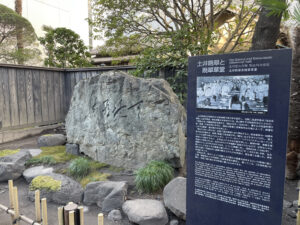【宮城県仙台市】「文化横丁」の読み方や語源・由来をたずねるin青葉区

仙台市青葉区一番町。東一番丁通りと南光院丁通りに挟まれたこの界隈には、昼と夜で表情を変える路地がある。「文化横丁」——その名を初めて耳にしたとき、私は地域文化ライターとしての好奇心を抑えきれなかった。文化という言葉が地名に冠されることは珍しく、そこには必ず何かしらの思想や歴史が込められている。地元の学生や住民からは「文横」と呼ばれ愛されている。仙台の中心部に、なぜ「文化横丁」という名が生まれたのか。その由来を探ることは、仙台という都市の成り立ちと、そこに暮らす人々の営みを知ることにつながる。
文化横丁は、仙台のメインストリートとも言えるサンモール一番町商店街のすぐ裏手、壱弐参(いろは)横丁と並ぶように存在する。昼間は静かな通りだが、夕方になると赤提灯が灯り、居酒屋やスナック、寿司屋、中華料理店などが活気づく。昭和の香りが色濃く残るこの路地は、観光客よりも地元民に愛される「通の場所」だ。私自身、学生時代は仙台駅前や広瀬通り、国分町で飲み歩いていたが、社会人になってからこの文化横丁の魅力に気づき、何度も足を運ぶようになった。
この横丁には、ただの飲食店街以上のものがある。店主と客が言葉を交わす時間、常連が集う空気、そして路地に漂う人情——それらは、仙台が誇る「サロン文化」の原点でもある。今回は、文化横丁の地名の由来を中心に、仙台の路地文化の魅力を探ってみたい。
参考
MMTミヤギテレビ「科目は「歴史」 壱弐参(いろは)横丁の歴史」
東北大学「文化横丁 - TBA wiki」
文化横丁(仙台市青葉区一番町)
所在地:〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4−16
文化横丁の読み方・語源・由来
「文化横丁」と書いて「ぶんかよこちょう」と読む。仙台市青葉区一番町二丁目、東一番丁通りと南光院丁通りの間に位置するこの横丁は、昭和レトロな雰囲気を色濃く残す飲食店街として知られている。地元では「ブンヨコ」の愛称で親しまれ、壱弐参(いろは)横丁と並び称される仙台の“ディープスポット”だ。
文化横丁の名称の由来は、大正14年(1925年)に東一番丁通り沿いにオープンした映画館「文化キネマ」にある。この映画館は、当時の仙台市民にとって娯楽の中心であり、活動写真(映画)を通じて文化的な刺激を受ける場だった。映画館の脇にあった通りが「文化横丁」と呼ばれるようになり、やがてその名が定着した。
さらに遡ると、文化横丁の原型は大正13年に誕生した「東百軒店街」にある。この店街は、戦前から戦後にかけての仙台の商業活動の中心であり、戦災後の復興期には露店やバラックが並ぶ場所として再生された。壱弐参横丁と同様に、文化横丁も仙台空襲後の混乱期に市民の生活を支える場として機能し、現在の姿へと発展していった。
このような歴史背景は、沖縄・那覇市の牧志公設市場とも通じるものがある。私自身、牧志市場には何度も足を運んでいるが、市場の周辺には小さな飲み屋街が広がり、戦後のバラック文化が今も息づいている。文化横丁もまた、戦後の混乱期から立ち上がった人々の営みが形になった場所であり、路地の奥に人情と生活の記憶が残っている。
文化横丁には現在、50軒以上の飲食店が軒を連ねている。寿司屋、中華料理店、スナック、居酒屋、バー——その業種は多岐にわたり、昼飲みから深夜の一杯まで、さまざまなスタイルで楽しめる。昭和の面影を残す店構えと、現代の感性が融合した空間は、仙台ならではの文化の発信地でもある。

参考
仙台メディアテーク「文化横丁」
まとめ
文化横丁を歩くと、そこには仙台という都市の記憶が静かに息づいている。赤提灯の灯り、狭い路地、店主と客の何気ない会話——それらは、ただの飲食店街ではなく、仙台の復興と文化の象徴だ。「文化横丁」という名には、大正期の映画館「文化キネマ」に由来する文化的な響きと、戦後の混乱期を乗り越えた人々のたくましさが込められている。
この横丁は、東一番丁通りと南光院丁通りに挟まれ、壱弐参(いろは)横丁と並ぶように存在する。サンモール一番町商店街の裏手にありながら、独自のにぎわいを見せるこの路地は、観光客よりも地元民に愛される「通の場所」だ。昭和の香りが色濃く残るこの空間は、仙台が誇る「サロン文化」の原点でもある。
仙台の食文化——牛タン、テールスープ、炉端焼きなど——も、このような横丁文化から生まれたとされている。米軍が食べなかった部位を無駄にせず、じっくり焼いて提供する中で、店主と客が言葉を交わす時間が生まれた。そこから育まれたのが、仙台独自の「サロン文化」だ。人と人がつながり、語り合い、文化が生まれる場。それが文化横丁であり、仙台の誇りでもある。
地名に耳を傾けることで、私たちは過去と現在をつなぐ静かな声を聞くことができる。文化横丁という名を辿ることで、私は仙台の復興と文化の力強さに触れることができた。これからも、この町の灯りが消えることなく、次の世代へと語り継がれていくことを願ってやまない。
青葉区の地名には、読み方の難しさとともに、土地の記憶が宿っている。「定義山」「晩翠通り」「壱弐参横丁」など、それぞれに物語がある。特に定義山は、地名と信仰が重なる象徴的な存在であり、別記事にて詳しく紹介している。
投稿者プロ フィール

-
地域伝統文化ディレクター
宮城県出身。京都にて老舗和菓子屋に勤める傍ら、茶道・華道の家元や伝統工芸の職人に師事。
地域観光や伝統文化のPR業務に従事。